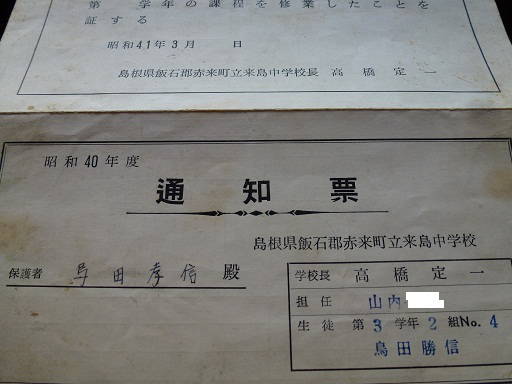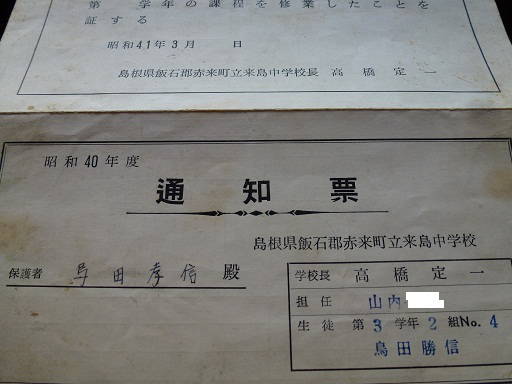頑張っても頑張っても、勉強も運動も、その他の諸活動も、なかなかうだつが上がらない生徒がいます。
スポ小バレーでも、アタックを教えたその日に、既に「形」になる子がいます。一方では、半年経っても「アタックの形」にならない子もいます。神様のイタズラとしか思えません。
しかし思います。人間、そういう学校時代の「成績」「成果」では評価しません。どんな職業にあっても、いちばん大きな要素は「人間性」です。優しさ・あたたかさ・思いやり・勇気・根気強さ・責任感・前向きな姿……、そういう人間的魅力で評価します。
児童・生徒に陰に陽に大きな影響を与える教師は、けっして「成果」のみで児童・生徒を評価すべきでは、当然ありません。
子ども達は「依怙贔屓」に敏感です。でも偉いですね、遅れがちな子・問題を抱える子などに対して教師が「えこひいき」しても、まわりの子は決して文句を言いません。逆に応援してくれます。

スポ小バレーを指導していた時期、練習中にあえて保護者にも聞こえるように、子ども達に話してきました。
「バレーが上手になることも、もちろん大事だ。それを目指して、今も頑張っている。それと同時に、いや、それ以上に重要なのは、バレーに取り組む姿だ。将来バレーを職業にする人は、ほんのわずか。じゃあ、スポ小バレーが終わって何が残るか? 辛くても苦しくても、なかなか上手にならなくても、ひたむきに一生懸命練習に取り組む、その姿。これは、将来に必ず生かされる。」(小学生には、もっと分かりやすい言葉で、……)
「いや、それは違うでしょう!」「そんなきれい事を!」と反論される保護者もあると思います。でも、私にとっては、この精神が(教員時代から)ずっと息づいているのです。
なお、社会人となれば「人間性」のみならず「成果主義」に翻弄される、厳しい現実の社会が待っています。そういう一面も、他方では伝えていく使命を、指導者は担っています。
成果を上げている生徒については、心の底から褒め称えると共に、今後に生かされるよう支援していく。
成果が上がらなくて下を向いている生徒(学力不振児・生活の乱れがちな子)には心から寄り添い、「えこひいき」も辞さない。良さを引き出し、認め、褒め、励ましていく。
|
. |
いつも出来たかというと、反省点も多々あります。が、奉職以来、現在に至るまで「私の座右の銘(指針)」の重要な一つです。