2023.2.11

コメントの部屋へもどる
2021.05.23 コンパクトシティ
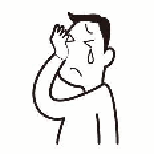
先日の教育委員会定例会で
社会体育施設の超寿命化計画(案)
が提示されました。
分厚い資料で
次回定例会までに読み込んで
意見をよろしくとのこと。
町内には
体育館・野球場・プールなど
こんなに沢山の社会体育施設があるものかと
改めて驚きました。
とともに
これを全て維持していくためには
気が遠くなるような予算が要ります。
ふと
コンパクトシティ
という概念が脳裏に展開しました。

コンパクトシティ
|
国立社会保障・人口問題研究所によると、2040年までに日本の人口は16%減少することが予測されています。人が減るなかで、持続可能な都市の姿として「コンパクトシティ」に注目が集まっています。
コンパクトシティとは、郊外に広がった産業や生活機能を一定の範囲内に集中させるという構想です。
近い将来、懸念される課題は地方自治体の財政状況の悪化です。出生率が下がり少子高齢化も拡大していることで、税金を納める層が減少している地域が増加しています。
高齢者の介護など福祉サービスなどの需要は増える一方、あてられる予算は限られてしまいます。さらに、財政が厳しい自治体にとって公共施設や道路、上下水道の整備など社会資本の維持管理費用も大きな負担です。
人口が増加し、経済も成長過程の頃は問題ありませんでした。しかし、人口減少時代に突入した今、このままでは財政破綻する自治体が出てきてしまいます。
|
.
|

以下は
先日NHKテレビで
小特集した時の内容(一部)です。
|
年末年始に多くの人々が帰省し、くつろいだであろう実家。しかし近い将来、その実家の処分に頭を悩ます時代が来るかもしれない。
人口減少が進む中、売ることも貸すこともできず、税金を払い続けるだけの「負の遺産」になりかねない。すでに空き家の問題は、全国で深刻化し始めている。今や7〜8軒に1軒は空き家、今後も急増すると予測されている。
また、都市部でも中古住宅より“新築住宅”を優遇し続けてきた結果、住宅の増加には歯止めがかからず、さらに空き家を増やす要因ともなっている。
一方で、水道などインフラの維持費用の負担の増大から、コンパクトシティを目指す動きが加速しているが、先行きは見えないまま。
根幹が揺らぎ始めている日本の住宅政策、そして国土利用。空き家問題を入り口に、人口減少時代に向けた対策を考える。。
|
. |




空き家を生かした取組

町並みに空き家が目立つようになると
町も寂れますが
心も寂れます。
そういう空き家を活用した
交流スペースは
一つの打開策です。
デトロイトの例
|
車の生産工場で、かつては大繁盛したデトロイトでは産業不振に陥り、急激な人口減少を引き起こしました。今や空き家率が29%に達しています。
人口が減れば、税収が減ります。そうなると街灯も減り、警察官や消防士も減り、どんどん町は寂れていきました。町が寂れると、更に人口が減っていきました。
|
.
|

日本の将来を
のぞき見るような
デトロイトの変遷です……。
日本でも
|
秩父市では、空き家率が18.7%です。デトロイトと同じく、住民が減ることによって税収が減りました。税収が減るとインフラ整備が追いつかなくなります。
大仙市では、倒壊の恐れのある家屋(空き家)を、住民の苦情を受ける形で撤去しました。しかし、家主から撤去料が回収できていません。税収減の上にこの有様です。
|
.
|

いやはや
本当に困った現状です。
家が朽ちていく風景は
とても無惨で残酷です。
住むあてがない場合は
あっさり撤去した方が
どれほどスッキリしているかと思います。
が
その撤去費用が
バカにならないのです。
コンパクト化を!
|
国の施策は「コンパクト化」に移っています。面積(集落数)は変わらないのに人口減(税収減)の現状では、インフラ整備にも限界があります。高齢者支援も移動に時間がかかると効率が悪くなります。
そこで、この際、市町のなかで便利な場所(地域の拠点)に集まり住んでもらおうという施策が、コンパクト化です。先進事例として富山市があります。移転する人には助成金を出して、拠点かを推進しました。結果、地域の拠点に住む人が 28%から32%になりました。
ただ、不便な地区に住み続ける人もいます。こういう住民の心をどう汲んでいくかが、課題となっています。
|
.
|

人口減少は
不便なところから
徐々に広がっていきます。
高齢者介護のことや
インフラ整備のことを考えると
確かにコンパクトシティは
一つの打開策ではあります。
が
総論賛成各論反対。
わがことになれば
住み慣れた場所
住み慣れた我が家を
捨てるに忍びないというのが
人情です。
そこをどう打破するか
それによって
このアイデアの正否が決まります。
放置家屋が増えると……
|
放置家屋が増えると、トタンや瓦が飛んできます。ホームレスなどが住みつきます。放火もあります。空き巣も増えます。町が寂れます。
不思議な現象があります。空き家は820万戸もあるというのに、毎年新築が100万戸もあるのです。
家屋を壊して更地にすると、固定資産税が6倍に跳ね上がります。なぜそういうことになったんでしょうか?
土地の値段がウナギ上りしたバブル期、都会や近郊では土地代が高くて税金が払えないというケースが激増しました。そこで政府は特例措置として、家屋の場合は固定資産税を 1/6 にしました。その名残です。
|
.
|

空き家820万戸に対して
新築が毎年100万戸。
価値観の違いですね。
親子孫
3世代同居の時代は
今となっては
古き良き時代になりつつあります。
それにしても
我が家の固定資産税も
毎年40万円台を超したままです。
この家屋(新築時に税金は高額を払いました)
一方
田畑(人に耕作してもらっています)
山林(残土捨て場として年収6万円)
ほとんど収入はないのに
税金は払わないといけません。
アパートを借りた賃貸料が
毎月3.5万円
という感覚で諦めて
払っています。
打開策になりうるか?
|
家が建つと、家具・家電・車などが売れます。戦後、政府は景気対策で新築を促しました。焼け跡に新築が相次ぎました。そこへ復員兵が続々と戻ってきました。
昭和50年代は、ベッドタウンに新築ラッシュが続きました。最近は、その更に外側の郊外に新築が増え、新ベッドタウン化 しています 。それに伴って、高齢世帯のかつてのベッドタウンは空き家が増えています。
市町村は、こういう現状にあってインフラの整備が大きな負担となってきています。
フランスでは、あるエリア以外はインフラ整備をしないという施策を実行しています。狭いエリアに集中して人が住む社会を目指しているのです。はたしてこれが、日本版の打開策となりうるのでしょうか?
|
.
|

確かに
市町村どこに住んでいても
同じようなサービスというのは
限られた予算では
しょせん無理な話です。
この飯南町にはなくて
出雲市にはある施設・設備は
実に沢山あります。
大きな図書館
映画館
ショッピングセンター
総合病院
フィットネスクラブ(施設)
温水プール
………………
まだまだあります。
これらを
島根県内津々浦々に!
ということは
初めから無理な話です。
としたなら
老後は出雲市に住んだ方が
より豊かな生活が
出来るようにも思います。
更により大勢の人が
出雲市に移り住んだら
上記の施設・設備などが
更に利用者を増やします。
より格安で利用できるようになり得ます。
からからに
利害損得だけで考えたら
コンパクト化は
ベターな施策なのかも知れません……???

私の中でも結論が出ていません。
![]()
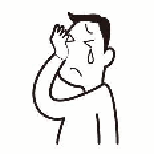
![]()
![]()










