要約学習の部屋に戻る
中学校教材の部屋へ戻る

像飯南町では答申を受けて
出来るだけ早い時期に
2つの中学校を1つに統合する
という方針で行政が動いています。
そういう中にあって
中学生を対象として
O教育長さんと合同で
「要約学習」の授業を実施することになりました。
授業最初の20分間は
準備した4教材を使っての学習です。
全体像
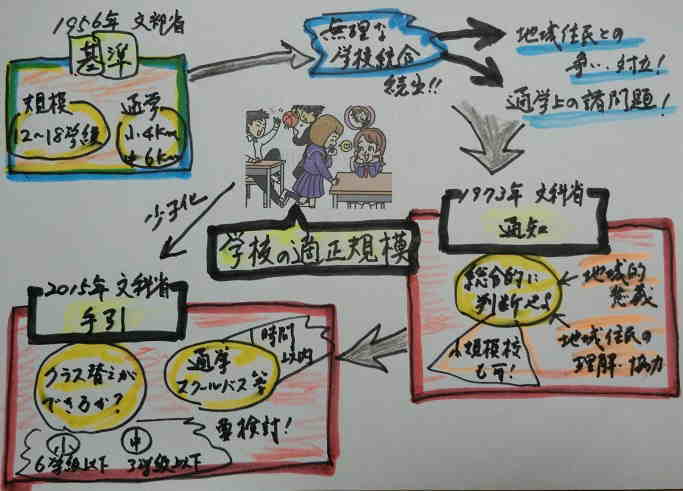
学校統合 学校の適正規模(№1) . |
2024.6.23
![]()
要約学習の部屋に戻る
中学校教材の部屋へ戻る

像飯南町では答申を受けて
出来るだけ早い時期に
2つの中学校を1つに統合する
という方針で行政が動いています。
そういう中にあって
中学生を対象として
O教育長さんと合同で
「要約学習」の授業を実施することになりました。
授業最初の20分間は
準備した4教材を使っての学習です。
全体像
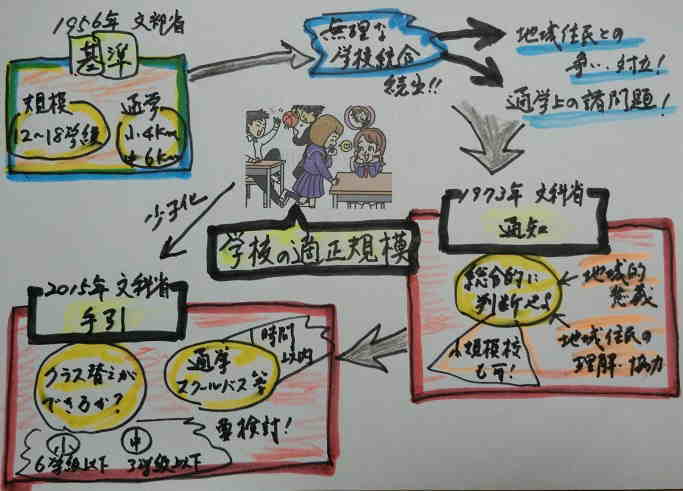

教材
|

図式化(個人学習)8分 ⇒4人グループ(相互プレゼン;40秒×3セット) ⇒全体代表プレゼン(計4人;4分) =合計時間 20分+アルファ |

|
この教材を使った学習
|
.