コメントの部屋へもどる
中学校を巡っては
今年度から3年間かけて
部活動が大きく変わろうとしています。
指導者(顧問)が
教員から地域指導者に移行します。
当面は
土・日曜日、祭日を目指します。
以下のように
要約学習の教材にもしました。
部活動の地域移行 . |
2023.6.11
![]()
コメントの部屋へもどる
![]()
中学校を巡っては
今年度から3年間かけて
部活動が大きく変わろうとしています。
指導者(顧問)が
教員から地域指導者に移行します。
当面は
土・日曜日、祭日を目指します。
以下のように
要約学習の教材にもしました。
全体像
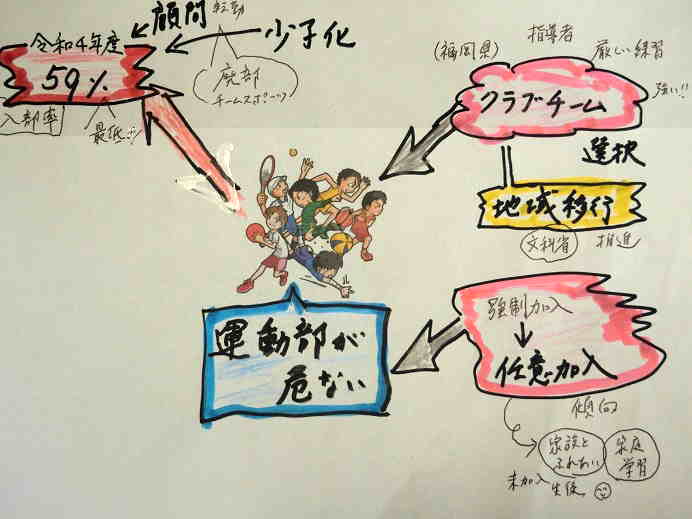

教材
|
|
生徒の意見は?
|
現実として……
|
打開策はあるのか?
|
都会的発想
|
ピンチはチャンス
|