コメントの部屋へもどる
子どもが支配されて育ったら . |
2021.9.29
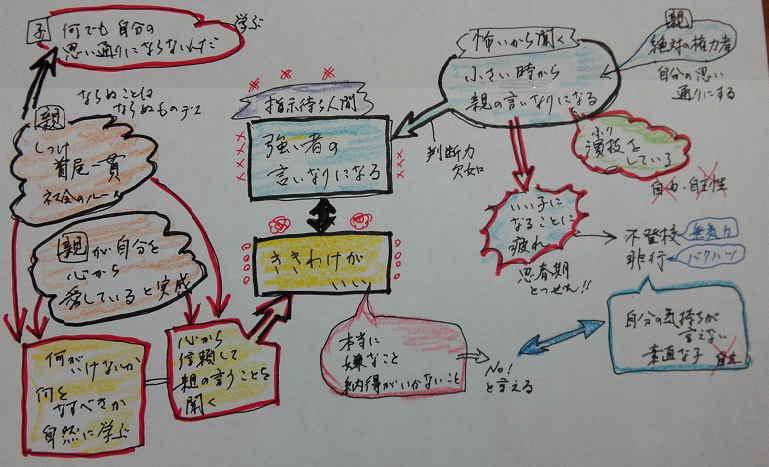

先日
『ちゃんと話が聞ける子に』(田中喜美子)
を読みました。
新入生に向かって「ハイ皆さん」と
(小学校)学級担任が呼びかけても
ちゃんと聞いている子は
半分しかいない。
こんな嘆かわしい実態から
この本は始まっています。
わが子(男42・女38・男37)のことや
教員生活時代に出会った子ども達のことと
ダブらせながら読みました。
多少???の部分もありましたが
大半は「そうだそうだ」と
納得したり思い返したりしながら
読み進めました。
いつものように
A5に図式化しながら読みました。
上の写真は
5枚中№1(1枚目)です。
今回はこの本の内容(№1)に関わって
コメントを書くことにしました。
![]()
再掲
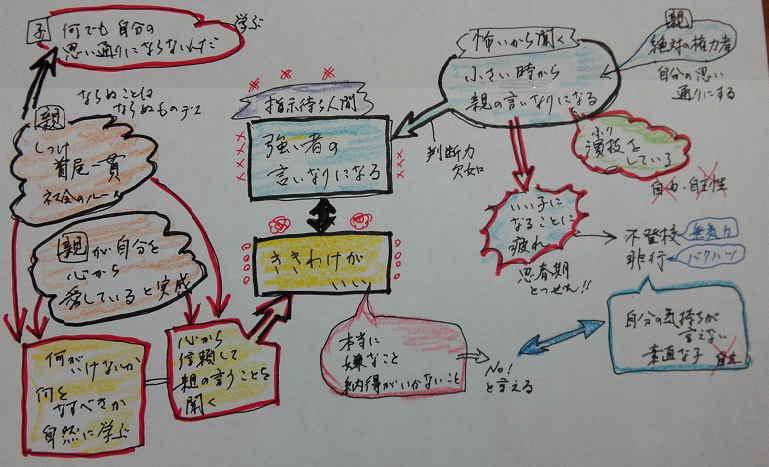
聞きわけがいい子
|
子どもが支配されて育ったら?
|