コメントの部屋へもどる
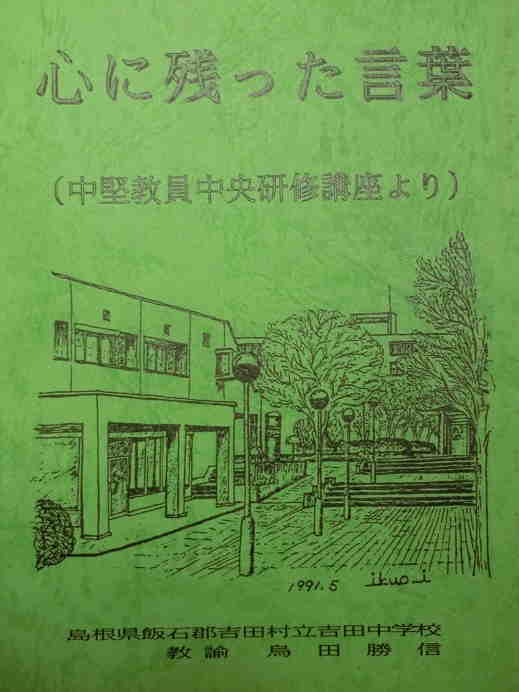
自分の体を通り抜けた文章 . |
2021.4.11
平成3年5月7日から6月11日までの36日間
国立教育会館筑波分館で開催された
第168回教職員等中央研修講座(平成3年度中堅教員研修講座)に
参加する機会を得ました。
北に筑波山を望み
木々の緑と抜けるような青空に囲まれた
広々とした学園都市に位置する
国立教育会館筑波分館.
ここに、全国から参加してこられた
299名の先生方とともに積んだ研修は
大きなインパクトを与えられました。
私の教育観、人生観を変えました。
なかでも合計41回に及ぶ講義は
各界一流の先生ばかり
思わず時間を忘れて聞き入るものばかりでした。
これまでの私の生き様を振り返り
これからの教師としてのあり方を模索する
貴重な機会となりました。
ところで
この研修会に際して
『心に残った言葉』と題して
個人的に一冊の冊子を作製しました。
その「まえがき」の部分を以下に転記します。
●講義を聞きっぱなしにすることと
それを文章化しながら
○内容を再吟味すること
○自分自身を見つめること
その両者の違いを認識する
思いがけない機会となったことを
この「まえがき」に書いています。
この発見は、
今でも貴重な体験として
私の財産となっています。
『心に残った言葉』
まえがき
〜自分の体をとり抜けた文章〜
|
以下は、冊子『心に残った言葉』から引用しました。
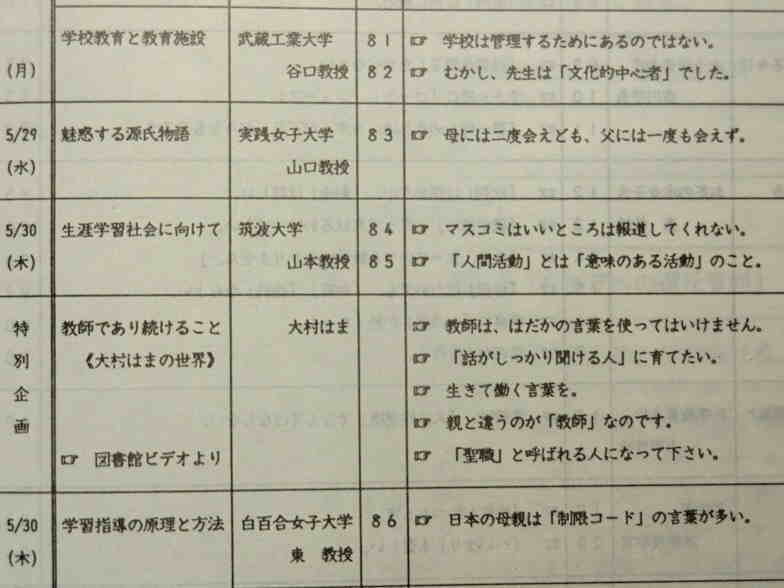
開講式より
「教育は人にあり」
|
「甘える」「甘やかす」
という言葉は欧米にはない
放送大学 祖父江教授
|
褒めて、けなして、また褒めて
放送大学 祖父江教授
|
この他に
41講義のうち
105のタイトル
109ページの冊子として
約50冊を作製して
お世話になった方に贈りました。