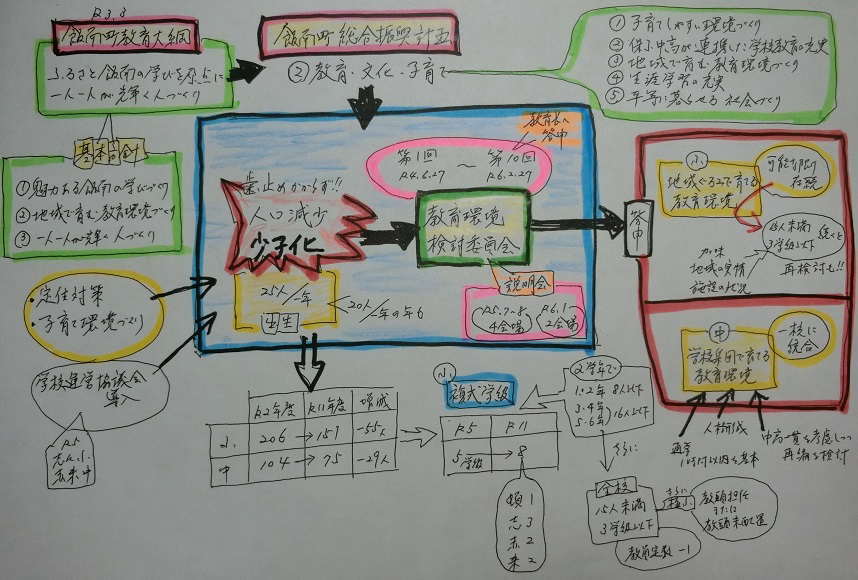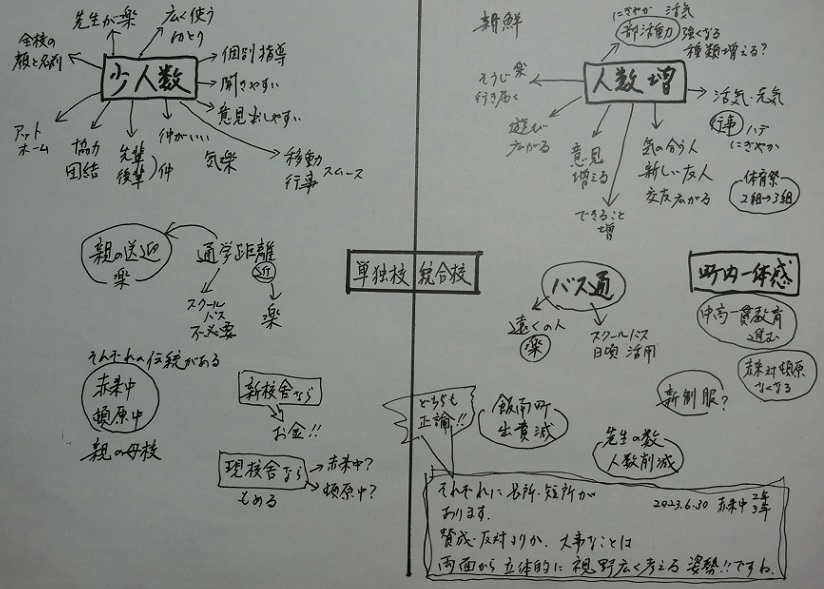�R�����g�̕����ւ��ǂ�

�������R�N������
�ѓ쒬�������w�Z�̓��p���ɂ���
��c���P�O��d�˂ċ��c���d�˂Ă��Ă���
�ѓ쒬����������ψ��
�Q���Q�U���i�j
��J���璷�ɓ��\�Ă���n����܂����B
���̎ʐ^��
���̂��Ƃ���V���̋L���ł��B


���̓��\�Ă�
�`�S���P�T�y�[�W�ɂ킽�钷���ł��B
�W�����ēǂ�ł��Ă�
�r�����瓪�����炭�炵�Ă��܂��B
������
���\�Ă��ȗ��������}���ɂ��܂����B
�ȉ��̒ʂ�ł��B
�S�̑�