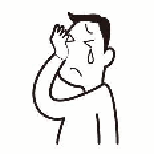2023.11.19

コメントの部屋へもどる
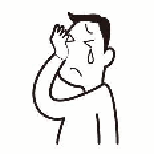
平成13年と20年の文部科学省の調査結果から
フリースクールも含めて
中学校を不登校状態のまま卒業した場合には
20歳時点での生活状態は
少なくとも半数程度
ニートかフリーターで
約2割がひきこもることがわかっています。
確かに
学校へ行かない選択も
あるとは思います。
強制は出来ません。
しかし
二度と戻ってはこない
かけがえのない児童期や青春時代です。
集団生活の中で学ぶこと
集団生活の中でしか学べないことなど
学校で学ぶべき事は十指に余るほど
沢山あります。
私は
不登校の子ども達には
何としても学校に通ってほしいと
強く強く願っている一人です。
不登校
過去最多
|
文部科学省は2023年10月4日、「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果を公表した。
調査結果によると、小・中学校における不登校児童生徒数は299,048人(前年度244,940人)であり、前年度から54,108人(22.1%)増加し、過去最多となった。
|
. |

不登校になる理由10選
【2022年最新版】
1位:人間関係
2位:無気力
3位:勉強の遅れ・成績が悪い
4位:学校に馴染めない
5位:家族関係や家庭環境
6位:朝起きられないなど生活の乱れ
7位:原因が自分でも分からない .
8位:身体の不調
|
.
|
引用サイト
不登校になる原因ランキング10選│
原因がわからないときの対処法を解説!
ウェルカム通信制高校ナビ (tsuushinsei.net)






不登校の原因
〜文科省の見解〜
|
子どもの数は毎年どんどん少なくなってきています。にもかかわらず、不登校の人数は毎年過去最高を更新し続けています。なぜ、このように毎年、不登校が増えているのでしょうか?
とりあえず、Googleでいくつかの記事を検索してみました。
まずは、文科省は「複合的な要因が絡み合っているので、原因を特定することは難しい」と言っています。日本の教育機関のトップは、どうやら「分からない」と言っているようです。以下、次のような意見が見られました。
|
.
|
社会の不登校への認知が高まったから
不登校が増えた
|
不登校が出始めた頃、私は正直「メディアのせいだ」と疑っていました。センセーショナルに取り上げるから、不登校予備軍が「じゃぁぼくも」式にどんどん増えるのではないか! と考えていました。
近年のメディアは更に、不登校を肯定する意見が増えています。親御さんとしても「無理してまで学校に行かなくていい」と考える方も増えているようです。
実際に「登校刺激は与えないように」というお達しが文科省から出されました。
|
.
|
いじめが増加したから
|
2023年10月3日、「文部科学省の問題行動・不登校調査」によると、全国の小中高校と特別支援学校で2022年度に認知されたいじめの件数が、前年度から1割増の68万1,948件に上り、過去最多となったとのこと。また、深刻ないじめの重大事態も217件増え、最多の923件だったと報道されました。
統計上について、過去、いじめの定義が変わってきています。
昭和61年度〜 学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。
平成6年度〜 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
平成18年度〜 「いじめ」とは「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
つまり、教師等の認知から、本人が苦痛を感じる(いじめだと思う)行為は全て「いじめ」とカウントすることへと変更になりました。昔はカウントされなかった「冷やかし」や「からかい」などもいじめとしてカウントされるように変わりました。
実際、いじめを受けてそれが苦痛で学校に行けなくなったり、中には自殺したりという悲惨な事例も少なからずあります。
ただ、いじめが全てかというと、それは違うと思います。私自身、(未だに誰にも話していませんが小学校高学年の時)近所のガキ大将からいじめを受け続けたことがあります。結論は、一対一のとっくみあいのケンカをして、それから収まりました。
|
.
|
最近の子どもが変わったから
|
この説は、記事の中で学校の先生や、発達心理学の専門家の方にインタビューしての結論となっています。
時代が変われば社会も変わり、家庭環境も変わり、保護者自身の変化もあり、…………その影響のもと、子ども達の変容は、それは当然の理だと思います。ここらについては、項を改めて述べたいと考えています。
いちばん危惧していることは、親も該当児童生徒も「不登校はふつう」と受け入れてしまっていることです。こういう心境がある限り、不登校から抜け出すことは難しいと思います。
|
.
|

ここからは批判覚悟で
日ごろから考えていることを
思い切って率直に書きます。
ただ
かなり長くなりそうなので
日にちを改めて
続きを述べることにします。