2023.3.11

コメントの部屋へもどる

一般的に
国語科の授業で「文学作品」を扱う場合
「三読法(通読⇒精読⇒味読)」が一般的です。
全国津々浦々
当たり前のように三読法が展開しています。
子ども達の立場に立ったとき
それが物語を読む醍醐味を
奪ってはいないでしょうか?
感動的な授業
|
私の初任校は各学年5〜6学級の大東中学校、国語科教員は6名(20代1名、30代1名、40代4名)。当時は初任研はありませんでしたが、毎週一コマ「国語部会」が設定され、教員同士の研鑽の場が保障されていました。
その校内研修の一環として、T先生が魯迅「故郷」の授業を公開されました。度肝を抜かれました。作品全体を通しての「学習課題を設定する」という授業でした。生徒から出された疑問点(みんなで考えたい課題)を絞り込む授業でした。休憩時間を活用して生徒たち一人一人が、黒板に解決してほしい課題を黒板いっぱいに板書しています。
授業が始まると教師がリーダーシップを発揮して、課題を絞り込んでいきます。簡単な疑問はその場で解決したり、同じような課題をまとめたり、下位の課題を排除していったり、……。授業終末には数個に絞られていました。驚きは課題を絞り込む過程で、読みがどんどん深まっていったことです。感動的な授業でした。
|
.
|
私の挑戦
|
以後、私も果敢に挑戦し続けました。が、いつも不消化。満足できる授業が実現しないまま4〜5年が経過しました。生徒からは授業が面白くないと、不満の声が聞こえていました。
いちばんの問題点は、優等生挙手発言。本文を読むことさえ覚束ない生徒は授業に参加したくても、教師が求めるレベルに達することが出来ず、ただ聞き役に徹するしかありません。(ここをおろそかにしたままにして)指導者(私)と、読解力のある生徒を中心に授業が展開していました。
|
.
|
一読総合法との出会い
|
授業は学力を伸ばすことと、知的喜び(楽しさ・醍醐味)と、この両輪が必要です。全員参加の授業を目指すことは、これは教師の使命です。授業者の私にとって、決定的な課題が克服できず悶々として月日を重ねていました。
そんなとき、書籍で「一読総合法」に出会いました。幸い、これが授業改善の突破口となりました。もっとも私が実践したやり方は、「一読総合法」の理論(学習指導過程)どおりではありません。少しずつ自己流に変えて行いました。
いちばんヒットしたのは、作品を通読しないことです。物語の醍醐味は、先がどうなるのかワクワクドキドキしながら読み進めることです。日ごろ、誰もが物語を読むときの喜びとしている「一読了解」をベースにしたスタイルです。
|
.
|
遅れがちな生徒も参加して!
|
短い文章を基に読み進めていくので、遅れがちな生徒も参加が可能になります。第2時間目は前時の学習をふまえて、これも短い文章を対象にするので、全員参加が可能になります。
日ごろ物語を読むのと同じように、読み進めるごとに情報が次々加わっていき、螺旋状にストーリーが膨らんでいきます。ある場面で立ち止まるときは、これまでみんなで読み味わった内容を基盤に「今」を読み深めます。
(学習課題によっては、予測が不可能なこともあります。こういう学習課題は、積み残したまま次の展開へと読み進んでいきます。日ごろの読みと同じパターンです。)
|
.
|
例えば
|
『走れメロス』の場合、最後はぎりぎり間に合ってたどり着くことが分からないから、途中立ち止まって考える面白さがあります。「山賊は王の回し者か?」、その場面までの流れや文章表現や字句一つ一つに着目しながら、子ども達は興味津々考えを巡らし、全員参加で授業が展開します。
小田小学校で3年生『サーカスのライオン』を扱った際、最後の場面のプリントを配ってみんなで読んだとき、子ども達が泣き出して、しばらく授業ができませんでした。これも、一読総合法のなせる業だと思います。
|
.
|
分析的な授業は?
|
国語の授業は、「文学評論家」や「作品研究家」を育てることにありません。あまりに分析的に授業を構成すると、物語の面白さを損ねかねません。私の大学時代の授業がそうでした。
子ども達には、物語を読む醍醐味を体感できる世界へ誘ってやることが大事です。一方、文学作品は学力テストで測れないという見解もあります。私立大学の「大学入試」では文学作品を扱わないケースが流れとなってきています。
|
.
|
入試に文学作品は出題されない
|
私は4年間、高校入試の作問に関わった時期があります。難渋を極めたのは文学作品です。作問委員5人の間で、解釈に違いが出ることはしょっちゅう。その度に長い沈黙と激論、自分自身の読解力を疑いながらほとほと疲れました。高校入試から文学作品を除いたらどんなに楽だろうかと、幾度も思いました。
実際、大学入試に於いては文学作品は出題されない傾向が鮮明になっています。以下は、朝日新聞(2011.12.8)「入試に小説なぜ出ない? 出題率わずか3〜5%」の記事です。
|
.
|



大学入試センター試験まで約1カ月。毎年、国語の長文読解問題で「小説」は必ず出題されているが、各大学の実施する入試に姿を見せることは少ない。なぜ、人気がないのか。
高校国語の授業では、小説の読解は定番だ。東京書籍の「現代文」教科書には、中島敦「山月記」や志賀直哉「城の崎にて」など、おなじみの作品が今も掲載されている。
だが大手予備校の代々木ゼミナールによると、国公立大学の約1割が、この5年、入試に小説を出題しなくなった。私立では近年、出題率が3〜5%程度。そもそも、文学者の文章からの出題が減る傾向にある。
代ゼミ教材研究センターの土生昌彦本部長は「必ず小説を出題する大学以外で突然、小説が出たらニュース」と話す。代ゼミの過去5年の調査によると、早稲田大では現代文100問のうち4問、上智大は69問のうち2問しか小説の出題がない。
学習院、明治、青山学院、立教、法政、中央の各大学でも、今年度の小説の出題は法政大の1問だけ。学習指導要領に準拠して出題するはずの国公立大でも、5年連続の出題は全体の19%にとどまる。
実際に国語の入試問題を作っている関西地方の私立大の教授も「小説の問題は作りにくい」と語る。
背景には、採点簡略化のため「選択式」問題が増えたことがある。小説は解釈の幅が広く、「こうも読める、ああも読めるため、選択肢が作りにくい」のだ。加えて選択式では、小説がよく読める人ほど解けないこともある、と指摘する。
例えば友人に「バカ野郎」と叫んだ主人公の心理を問うとき、それが怒りとも親愛の情とも取れる場合がある。「親愛の情の表現」と解釈したのに、その通りの表現が選択肢にないと「選択肢と自分の解釈との微妙な違いを感じて迷う生徒がいる」らしいのだ。
私立大教授は「答えがまぎらわしくなりそうな時は、評論的な合理性がある部分から設問を作らざるを得ない。でもそれだと小説を出す意味がなくなる」と、葛藤している。
別の理由を挙げる人もいる。早稲田大教育学部の石原千秋教授は「小説の出題は道徳の問題」と考える。
例えば「殴る」という行為が描かれた小説をどう読むか。「実は愛情を持っているという道徳を出題者と解答者が共有していなければ、ただの暴力としか読めない」と指摘する。共通した道徳がなければ読解問題を作りにくいというのだ。
小説が減り始めた転機は1980年ごろにあったようだ。「以前は、道徳的な共通解釈が出題者と解答者の間に共有できていたから出題できていた。多様な価値観が広がり、解釈も一つではなくなった」と話す。
では毎年小説を出しているセンター試験はどうなのか。「あれは設問文を長くすることで、設問自体の読解力があれば解けるようになっている」と手厳しい。
石原教授は提案する。国語でなく「文学」という科目を設けてはどうか、と。
戦後、GHQが「芸術」という科目を作ろうとしたことがある。美術や音楽と同じように、文学を学ぶ教科だ。「文学」の授業は文学者が各校を回って性や暴力をテーマにした小説も取り上げ、自由に読ませる。心を採点することになるから、正否はつけない。「あえて小説を入試に出すなら、自由に解釈を書かせて、採点者の好みで大学が求める個性を評価するしかない」と石原教授は話す。
一方、作家の阿刀田高さんは「やはり小説は国語に残してほしい」と言う。母国語は単にコミュニケーションの道具ではなく、「脳そのもの」と考えている。合理的な評論ではなく小説を学ぶことは「人間の曖昧(あいまい)で計り得ない部分を探ることにつながる」と指摘する。
そんな曖昧さを、入試で問えるのか。阿刀田さんは「曖昧な部分があるのが文学。芥川賞や直木賞の選考とは違うのだから、記述式にすれば普通に良いものは採点できます」と話す。
|
.
|
読書が大好き!
|
こういう現状にあるだけに、学校現場ではいっそう「物語を読む醍醐味、面白さを体感できる世界へ誘ってやる」授業へと転換するべきだと、私は考えています。
国語の授業は、「文学評論家」や「作品研究家」を育てることが目的でも、入学試験で点数を上げることが目的でもありません。授業が終わったら、自然に自主的に子ども達が物語の本を借りたり読んだりする、その基盤づくりこそ、授業の使命だと私は考えています。
|
.
|
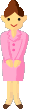
正式な「一読総合法」においては、
学習指導過程において
「一人読み」「書き出し」「書き込み」などが盛り込まれます。
私が行ってきた授業では、
そういう面については取り入れていません。
教科書はこちらで預かり、
最初から場面ごとにプリントの形で、
子ども達に作品を与えるという手法です。
したがって
児童言語研究会の主唱する
「一読総合法」とは正式には言わないかも知れません。
以下
『一読総合法入門』から
要約しながら一部を抜粋します。
一読総合法の誕生と方法
|
一読総合法は、横浜市・奈良小学校の校長であった林進治氏が、児言研での研究成果を土台として、全職員による実践をもとに理論化したことから始まりました。実践書が1964(昭和39)年に「一読主義読解の方法」として明治図書から出版されています。
児童言語研究会そのものは、戦後1951(昭和26)年に民主主義科学者協会を母体として生まれています。アメリカから導入された経験主義が横行する中で、言語能力の向上をめざして研究を開始しています。基礎学力の低下が叫ばれる中で、現場に登場してきたのは形象理論・解釈学でした。一般に「通読・精読・味読」という三読法の授業方式です。
こうした中で児言研は、1962(昭和37)年、言語学の学習から「三読法」への批判を打ち出し、「一読総合読みの理論」を創造し、授業実践に移すことになったのです。
「一読総合法」と他の指導法との一番の違いは、「初めの通読をしない」ということです。「一読」という言い方はこの読みの過程に由来があります。ということは、はじめから詳しく読み進めていくことになります。
どうして「初めの通読」をしないのでしょうか。まず本を読む楽しさを考えてみましょう。物語などを読んでいて一番心が動くのは、初めに読んでいる時です。「この先どうなるのだろう」とハラハラドキドキしながら読んでいるはずです。初めに通読をしてしまうと、推理小説の犯人が初めから分かっているようなものです。
一つ目の理由は「初めの通読は、読みの興味を奪ってしまうのではないか」ということです。
子どもたちが図書館で本を借りて読んでいる場面を考えてみましょう。子どもたちは、初めに通読をして、それから場面ごとに詳しく読んで、最後に味わうためにもう一度読む、などという読み方をしているでしょうか?
そうではないはずです。初めから最後まで読んでしまって、「おもしろかった」と思うか「つまらない本だった」と思うか決まってしまうはずです。ということは、初めに読んだ時に、どれだけのことを本から吸収できるかが重要なことになります。初めに読むときに自分の最大限の力を発揮して本に取り組む、それを授業で実現しようとするのが「一読総合法」です。
第一読から集中するためには、「諸作業」を展開することになります。その「諸作業」とは、例えば、次のようなものです。
まず、「題名読み」(予想・見とおし)の過程です。
次に、最初の「立ちどまり読み」(教室の一時間で完結する範囲)の過程に入り、ここから次のような学習が展開します。
「書きこみ」作業(読みの反応)、
「書き出し」作業(分析・総合したこと)、
「感想・意見出し」作業(話し合い)、
「話しかえ」作業(くわしい話しかえ・短い話しかえ・創作話しかえ)、
最初の立ちどまり部分の「小見出しづけ」作業、
「次の部分の予想・見とおし」作業、
「表現読み」の作業、
2番目の「立ちどまり読み」の過程も同じ展開ですが、違うところは、前の部分との「関係づけ」作業、「プラン作り」作業が加わることです。
最後の「立ちどまり読み」の過程でも新たに、「副題づけ」作業、「全文章の話しかえ」作業、「全文章の感想・意見記述」作業などが加わります。
|
. |

「一読総合法」では、
教師主導型からの脱却を図り、
児童・生徒の主体性を重視する中で、
読者として作品と対峙していく、
その姿勢と力を培っていきます。
このことについても、
一部抜粋しながら紹介します。
教師主導型からの脱却
読みの力を育てるということは、的確に文意を読み取り、読者として作品と対話していく力を育てることです。ですから作品の主題やテーマ、主張を的確に読み取る力を育てることはとても重要です。
かと言って、指導者から子どもたちへ一方通行に教え込んでも、学び取る力は育ちません。間違いながら、迷いながら、目標に近づいて行けば良いのだと思います。
「それぞれの読み」と「主題」については、さまざまな立場のさまざまな考えがあります。いずれにしても、最終的に「読者としての読み」の成長・発展が、最も重要なことです。一読総合法は、そのための方法なのです。
その際、「子ども任せではないか」「言わせっぱなしではないか」という指摘を受けることがあります。
その点については、「指導者がレールを敷いて、その通りに子どもを動かす」ことが良い指導だとは思えません。子どもの主体性や意識化が重要なテーマです。子ども達が主体性を発揮できるように環境を整えたり、経営したりすることが、教師の指導性です。
|
.
|
新鮮な最初の読みを大事にした
国語の授業を!
物語など文学作品を授業で扱って、どんな力を付けていくのか?
中学校で教壇に立っていると、ともするとペーパーテストで点数を取ることに気持ちが行ってしまいがちです。しかしながら本来あるべき姿は、文学作品の楽しみ方を学び、読み深め方を学び、そういう過程を通して「読書の魅力」を体得していくことです。
漢字力、語彙力など読解力に差がある子ども達。そのことにも配慮しながら、「文章を自力突破していく力」も付けなくてはいけません。
そして、「一読総合法」の趣旨の一つは、日頃の「読書の姿(一読了解)」に、より近づけた授業展開をすること。わくわくする新鮮な心を維持したまま、作品を読み進めることです。
教育事務所に勤務中の4年間、この「一読総合法」で行われた授業は、一度も拝見する機会がありませんでした。でも、私自身の授業体験から、もっともっと「三読法」以外の方法に挑戦されることをお勧めします。
|
.
|




![]()
