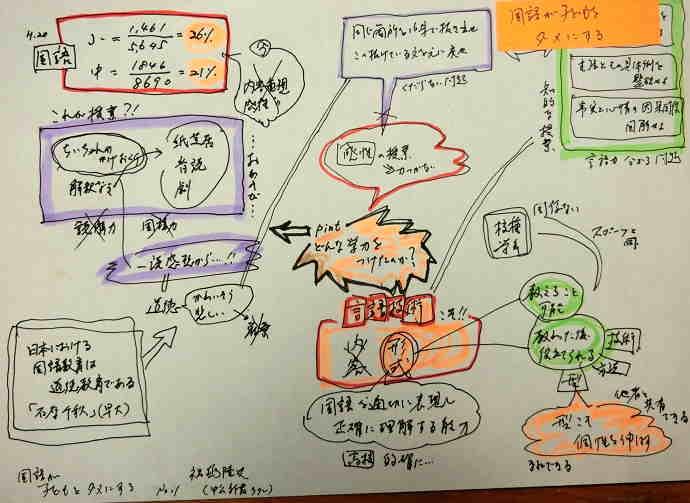コメントの部屋へもどる
退職後 (その1) . |
2022.7.30

平成23年3月31日
赤来中学校を最後に
教員生活にピリオドを打ちました。
その後
過ぎ去ってしまえば
あっけなく時は流れ
退職後12年目を歩んでいる私です。
こういう時期にあたり
この間の来し方行く末について
思いめぐらそうと考えました。
今回は
その第一回目とします。
(何回続くか不明)
退職翌日の朝
|
退職後の仕事
|
野菜づくり
|
読書
|
読書の記録:例
(図式)