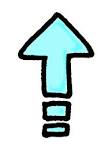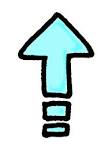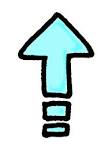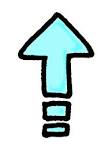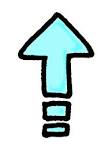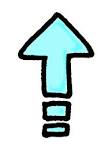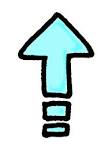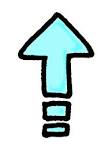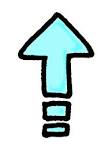「論理的思考力を適切に展開していくとき、情緒力が基盤として重要」との指摘、全く同感です。これは極端ですが、……詐欺を遂行するために「論理的思考力」を発揮するような「情緒」の持ち主は困ります。
一週間前、「コメントの部屋」に「高次の情緒力を育てるために」というタイトルで掲載しているのが、背景が黄色のの文章(部分)です。
 2020.8.23 高次の情緒力を育てるために
2020.8.23 高次の情緒力を育てるために
「言葉なしの思考」というものは存在しません。言葉を使わずに考えめぐらすことは不可能です。まさに言語力のレベルは、思考力のレベルと比例しています。
一方、「高次の情緒力」という概念があります。この言葉は、「国語分科会国語教育等小委員会」(平成15年)の議事録で登場しました。高次の情緒力(例えば、他人の痛みを自分の痛みとして感じる心、美的感受性、もののあわれ、家族愛、郷土愛、名誉や恥など)は、後天的に獲得されるものです。しかも、体験を通してというよりは、(教養がそうであるように)「(特に文学作品の)読書を通して培われる」ものとされています。
さらには、思考をめぐらす基盤となる「語句・語彙力」こそ、高次の情緒力と論理力を根底で支えています。いずれにしても、「読書離れ」は「高次の情緒力」「論理的思考力」の欠如を招くと、この小委員会の報告書で警鐘を鳴らしておられます。
|
. |
「読み聞かせ」が、その延長線上に「自力読書」とはなりません。が、私の把握する限り、(勤務校におけるアンケート調査によると)「読み聞かせ」を日常的にしてもらった子ども(中学生)は、おおむね20%程度でしかありません。
世の中の大人は、忙しくなってきていることは確かです。が、言葉や情緒の成長は、親子のコミュニケーションが基盤です。親が熱心に語りかけたり、子が一生懸命自分の体験や思いを伝えたりする、その積み重ねが、情緒力・論理的思考力・語彙力を育てている真実を、もっともっと世の親は認識する必要があります。