コメントの部屋へもどる
今を生きる . |
2021。6.27

今回は心理学者「アドラー」の名言を取り上げます。
|
人生は極めてシンプル
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
過去に縛られてはいけない
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
相手を変えようとしない
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
他人の目
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
動機や目的は「善」であれ!
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
褒めるのではなく……
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
相手を支配する
|

|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
他の人を喜ばせる
|

|
2021.6.17 実施
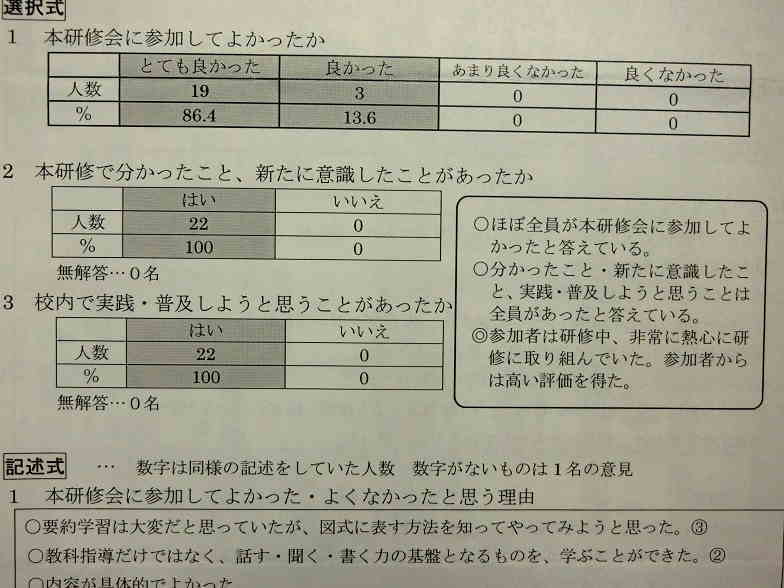
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
自己満足でじゅうぶん
|

|